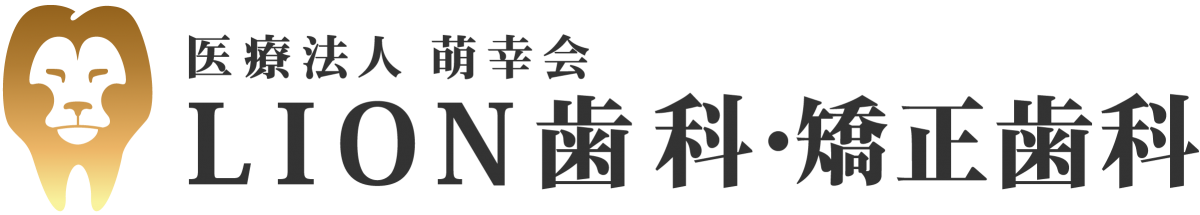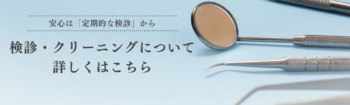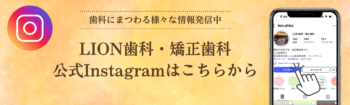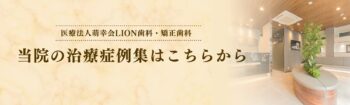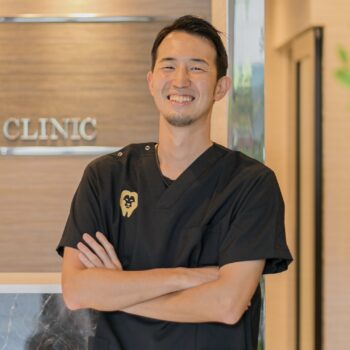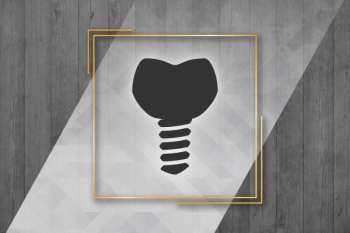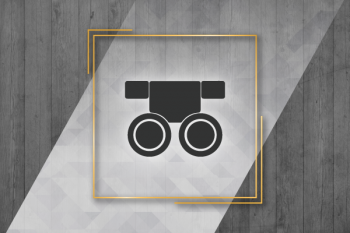歯の摩耗ってなに?すり減りの原因と予防法を解説
症状から記事を探す
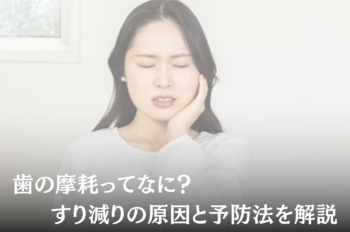
「なんとなく歯が短くなった気がする」「冷たいものがしみるようになった」
こうした症状が気になる方は、歯の摩耗(まもう)が進んでいるかもしれません。
歯の摩耗とは、何らかの原因によって歯の表面がすり減ってしまう現象です。
見た目の変化だけでなく、知覚過敏やかみ合わせの乱れ、むし歯リスクの増加などにもつながるため、放置せずに早めの対応が大切です。
今回は、歯科の現場で実際に見られる摩耗のパターンと、その原因、予防のために日常で気をつけたいことを詳しくご紹介します。
歯の摩耗とは?
歯の表面は「エナメル質」という人体の中でもっとも硬い組織で覆われていますが、それでも長年の刺激によって徐々にすり減っていくことがあります。
これを歯の摩耗(tooth wear)といい、すり減った部分から中の象牙質が露出すると、知覚過敏やむし歯になりやすくなるほか、歯の形そのものも変化してしまいます。
摩耗は加齢に伴って少しずつ進行しますが、生活習慣や癖によっては20代や30代でも明らかな摩耗が見られるケースも珍しくありません。
摩耗には種類がある
歯の摩耗には、原因によっていくつかの分類があります。
それぞれに特徴と対策が異なるため、自分の症状と照らし合わせて確認してみましょう。
1. 咬耗(こうもう):歯と歯がこすれてすり減る
咬耗とは、食事や歯ぎしりなどによって歯と歯が物理的にこすれ合うことで起こる摩耗です。
特に問題になるのが、就寝中の歯ぎしり(ブラキシズム)や無意識の噛みしめ癖。
これらは強い力が長時間加わるため、エナメル質が削れ、象牙質が露出することもあります。
また、咬耗が進むと歯が短くなり、かみ合わせの高さが低下して顎関節や筋肉に負担がかかることもあります。
2. 酸蝕(さんしょく):酸によって歯が溶ける
酸蝕とは、酸性の飲食物や胃酸の影響で歯の表面が溶け出す現象です。
これにより、エナメル質がやわらかくなり、さらに摩耗しやすくなります。
・炭酸飲料・スポーツドリンクを頻繁に飲む
・酢や柑橘類など酸性の食品が多い
・逆流性食道炎がある(胃酸の逆流)
こうした習慣がある方は、酸蝕のリスクが高まります。
3. 楔状欠損(くさびじょうけっそん):歯ブラシ圧による摩耗
歯と歯茎の境目がV字にえぐれたように欠ける現象を「楔状欠損」といいます。
これは主に、力を入れすぎた歯磨きや硬い毛の歯ブラシの使用が原因です。
楔状欠損は見た目だけでなく、知覚過敏の原因にもなりやすいため注意が必要です。
摩耗を放置するとどうなる?
歯の摩耗は自然に治ることはありません。進行すると以下のようなトラブルにつながります。
・知覚過敏:象牙質が露出してしみやすくなる
・かみ合わせの変化:歯の高さが低くなり、顎関節に負担がかかる
・むし歯や歯周病のリスク増加:表面の防御力が低下する
・見た目の老化:歯が短くなり、口元の印象が変わる
特に前歯の摩耗は、笑ったときの印象を大きく左右します。
審美的な問題も含めて、気づいたら早めに対応することが重要です。
歯の摩耗を防ぐには? 5つの予防法
日常生活の中で、歯の摩耗を防ぐために気をつけたいポイントをまとめました。
1. 正しい歯磨きを身につける
・力を入れすぎない(ペンを持つような力加減で)
・やわらかめの歯ブラシを使用する
・歯磨き粉は研磨剤が少なめ・フッ素配合のものを選ぶ
2. 酸性の飲食物に注意する
・炭酸飲料や柑橘類はだらだら摂取しない
・飲食後すぐの歯磨きは避け、30分ほど間をあける
・食後は水で口をゆすぐ、あるいはキシリトールガムを噛む
3. 歯ぎしり・食いしばり対策をする

・ストレスを溜めない(睡眠や運動でリラックス)
・ナイトガード(就寝中のマウスピース)の使用を検討する
・昼間の噛みしめ癖に気づいたら、あごをゆるめる習慣をつける
4. 硬いものを無理に噛まない
・氷、硬いせんべい、スルメなどを噛む習慣は控える
・奥歯で強く噛む癖のある方は噛み合わせチェックもおすすめ
5. 定期的に歯科検診を受ける
・摩耗の進行状況をチェック
・歯並びや噛み合わせの問題も早期に発見
・必要に応じてナイトガードや補修治療の相談が可能
歯科医院での対処法
歯の摩耗が進行している場合、以下のような対応がとられます。
・ナイトガードの作製:歯ぎしりや食いしばりから歯を守る
・レジン充填や補綴処置:削れた部分を修復して見た目と機能を改善
・噛み合わせの再構築(咬合挙上):全体的なバランスを整える
当院では、患者様の症状や生活習慣をふまえて適切な治療法をご提案しています。
まとめ:歯の摩耗は日常の小さな習慣から始まる
歯の摩耗は、加齢だけでなく、日々のクセや生活習慣によっても起こります。
軽度であればセルフケアで進行を防げますが、放っておくと治療が必要になることもあります。
「歯が短くなった」「冷たいものがしみる」など、少しでも気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
早期に気づいて対策をとることで、健康な歯を長く守ることができます。