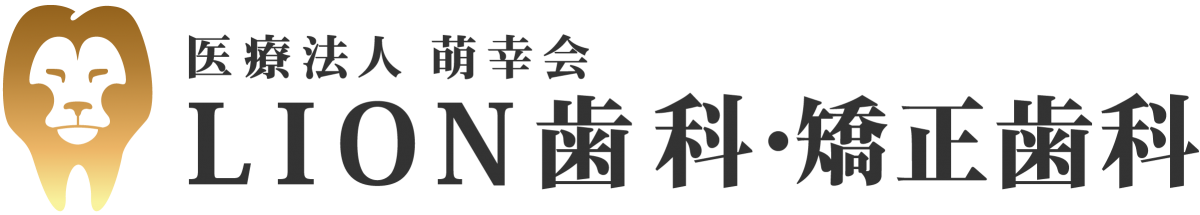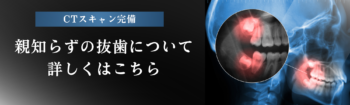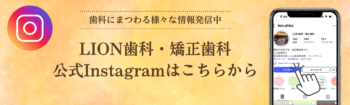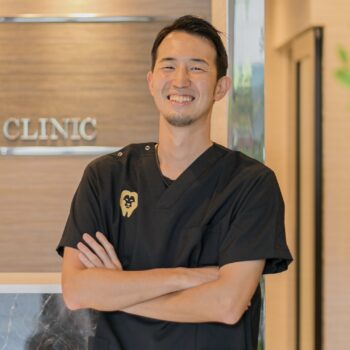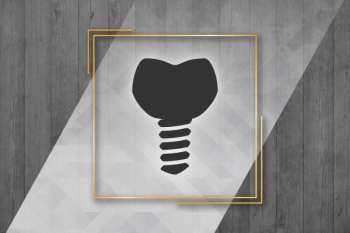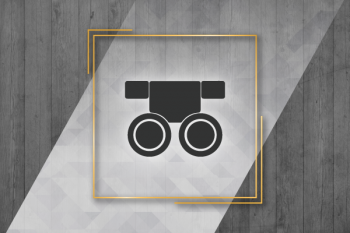親知らずの抜歯後の注意点は?
親知らず

親知らずの抜歯は、他の歯に比べて骨の中に深く埋まっているケースが多く、その分、腫れや痛みが出やすい処置です。
一般的に、抜歯後1〜3日目に腫れや痛みのピークを迎え、その後は徐々に落ち着いていきます。
おおよそ1週間ほどで日常生活に支障がなくなる方が多いですが、正しいケアや注意点を守ることで治りが早くなり、ドライソケットや感染などのトラブルを防ぐことが可能です。
腫れ・痛みのピークはいつ?
一般的に、抜歯後の腫れや痛みの経過は次のようになります。
当日〜翌日:麻酔が切れると痛みが出始める
1〜3日目:腫れと痛みのピーク
4〜7日目:徐々に落ち着く
1週間以降:多くの方は日常生活に支障なし
ただし、体質や抜歯の難易度によって差があります。
強い痛みが長引く、膿が出る、口が開かないといった症状がある場合は、感染や「ドライソケット(血餅(かさぶた)が剥がれた状態)」の可能性もあるため、早めの受診が必要です。
親知らず抜歯当日の注意点
親知らずを抜歯した直後は、傷口がとてもデリケートです。以下のポイントを守りましょう。
・ガーゼは20〜30分しっかり噛んで圧迫止血する
・強いうがいや、ストローを使った飲み物は避ける(血が止まりにくくなる)
・当日の入浴・飲酒・激しい運動は控える(血流が増えて出血や腫れが悪化)
・食事は麻酔が完全に切れてから、やわらかい物を反対側で食べる
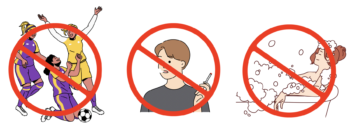
親知らず抜歯後1〜3日の過ごし方
・腫れてきた場合は、冷やしすぎない程度に頬を冷却すると楽になります
・痛み止めや抗生物質は、医師の指示どおり服用することが大切です
・傷口を触ったり、舌で触れるのは感染リスクにつながります
親知らず抜歯後の食事の工夫
親知らずの抜歯というと、どうしても「痛み」や「腫れ」に意識が向きがちですが、実は食事の内容も回復に大きく関わります。
抜歯後は歯茎や骨に傷ができている状態です。
その傷口に細菌が入り込むと、腫れ・炎症・発熱などのトラブルにつながることがあります。
そのため、抜歯直後から1週間程度は特に食事に注意が必要です。
おすすめ:おかゆ、雑炊、ゼリー、プリン、ヨーグルトなどの流動食
避けたいもの:熱すぎる食べ物、刺激の強い香辛料、炭酸飲料やアルコール
当日は麻酔が切れてから食事をとるようにし、傷口を刺激しないようにしましょう
痛みが続く場合の対処法

痛みが通常より長引く場合、以下の原因が考えられます。
①ドライソケット 血餅が取れてしまい、骨が露出する状態です。非常に強い痛みを伴うことがあります。ドライソケットが疑われる場合は、すぐに歯科医院を受診してください。
②感染 抜歯後の感染により痛みや腫れが悪化する場合があります。発熱や膿が出る場合は早急に相談が必要です。
歯科医院に相談すべきケース

以下の症状が見られる場合は、放置せず歯科医院へ相談しましょう。
・出血が24時間以上止まらない
・3日以上痛みが続く、また痛み止めが効かない
・過度の腫れや発熱がある
・抜歯部位から膿が出たり、強い口臭がある
よくある質問と回答
Q1. 抜歯後の痛みのピークはいつですか?
A.通常、術後24〜48時間が痛みのピークで、その後徐々に和らぎます。
Q2. 抜歯後の腫れはどのくらいで治りますか?
A.腫れは通常、術後3〜7日で引き始めますが、完全に治まるまでには1〜2週間かかることがあります。
Q3. どのくらいで普通の食事ができますか?
A.術後2〜3日程度で通常の食事に戻ることができますが、歯ごたえのある食品は、抜歯した歯の反対側で噛みましょう。
また、極端に辛いものや、香辛料が多く含まれている食品はしばらく控えましょう。
まとめ
親知らずの抜歯後は、1〜3日目に痛みや腫れのピークがあり、その後は徐々に回復します。
1週間ほどで日常生活に戻れる方が多いですが、注意点を守ることでトラブルを防ぎ、治りもスムーズになります。
親知らず抜歯後、気になる症状がある場合は我慢せず、歯科医院に早めにご相談ください。